 |
平成22年度 神崎郡歴史民俗資料館講座録集 |
|
 ≪平成22年度連続講座≫ ≪平成22年度連続講座≫
「地域の歴史文化遺産をつなげよう」
~郷土への誘い~
| 開 催 日 |
講 座 名 |
講 師 |
場 所 |
時 間 |
| 第1回 |
5月22日(土) |
福崎でつながる地域の歴史
~村史づくりの取り組みについて~ 済
*高橋部落史・板坂村史・田口村史・余田村史の紹介 |
松下正和氏
(神戸大学) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第2回 |
7月3日(土) |
日本の七夕・播州の七夕 済 |
尾崎織女氏
(日本玩具博物館 学芸員) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第3回 |
9月18日(土) |
福崎町の仏像をめぐって 済 |
神戸佳文氏
(県立歴史博物館 学芸員)
|
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第4回 |
11月13日(土) |
姫路藩大庄屋三木家の職務について 済 |
山﨑善弘氏
(神戸大学
地域連携センター) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第5回 |
2月19日(土) |
若狭・播磨・紀州をめぐる王の舞の事例研究 済 |
大渡敏仁氏
(芸術文化学博士) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
 平成22年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集 平成22年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集
<第5回 講座録>
日 時:平成23年2月19日(土) 13時30分~15時
演 題:「若狭・播磨・紀州をめぐる王の舞の事例研究」
講 師:大渡敏仁氏(芸術文化学博士)
2月19日、歴史民俗資料館にて、本年度第5回目の連続講座を開催しました。
今回は、近年和歌山県で調査を進められている民俗芸能のなかでも、
王の舞について、播磨や若狭地方も含めた事例をご紹介いただきました。
講座をとおして、各地の事例を知ることで見えてきたそれぞれの王の舞の特色や、
古来からの芸能を残す貴重な事例など今回はじめて知った事例も数多くあったのでは
ないでしょうか。
当町では、昨年70年ぶりに北野神楽が再興するなど、改めて民俗芸能のかけがえのなさ、
そして守り伝えていく大切さを実感します。
本講座では、こうした地域に残る民俗芸能の姿を現地調査によって記録された
貴重な映像や丁寧な分析により、理解を深めることができました。
これからも講座をとおして、地域の歴史や文化を見つめ、興味・関心を深めていければと
思います。
どうぞ今後ともよろしくお願いします。
<第4回 講座録>
日 時:平成22年11月13日(土) 13時30分~15時
演 題:「姫路藩大庄屋三木家の職務について」
講 師:山﨑善弘氏(神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター 研究員)
11月13日、歴史民俗資料館にて、本年度第4回目の連続講座を開催しました。
今回は本年度特別展でも紹介した江戸時代大庄屋をつとめた三木家に収蔵される、
三木家史料から、三木家の職務についてお話いただきました。
講座では、文政6年(1823)の『諸御用日記』という史料を紹介いただき、
この史料は、6代目当主三木藤作の職務日記であり、
大庄屋と代官、大庄屋と村々の関係などが分かり、三木家の職務の実態を
具体的に知ることができます。
江戸時代、私たちの村々に姫路藩からどのような触が伝達され、
村々はどのようなことを嘆願していたのかや、
私たちの先祖が三木家からおとがめを受けるようすも記されていました。
これらの話どれもが、当時のくらしを身近に感じることができ、
また、三木家が大庄屋として村々を治める姿が浮かび上がってくるようでした。
‘古文書史料’は難しいという認識から、今日話を聞くことで、
一つの史料につまった当時の情報を読み解く魅力を、
先生のお話から知ることもできました。
このような貴重なお話をいただき、どうもありがとうございました。
これからも三木家史料の魅力を先生に読み解いていただくことを楽しみにしています!
<第3回 講座録>
日 時:平成22年9月18日(土) 13時30分~15時
演 題:「福崎町の仏像をめぐって」
講 師:神戸佳文氏(兵庫県立歴史博物館 学芸課長・学芸員)
9月18日、歴史民俗資料館にて、本年度第3回目の連続講座を開催しました。
今回は「福崎町の仏像」について、近年行われた町内の仏像調査により
新たに確認された事例を紹介いただきました。
まずは町内で行われた仏像調査の内容を話しいただき、
現地での現状確認、時代や銘文等の確認、撮影などにより記録保存される大切さを
知ることができました。
そして様々な調査を経て江戸時代を中心とした町内の仏像事例や、
銘文により明らかになった、仏像を作った仏師の紹介など、
仏像をとおして新たな地域の歴史を知ることができました。
近年、文化財の盗難が多発し、とりわけ仏像の被害が多く報告されています。
地域の大切な文化財を守るには、まずは地元の文化財を知り、そして歴史背景をみていくことで、
地域の中で文化財を見守る目が養われるのではないかと感じることもできました。
町内の仏像調査へも協力いただき、貴重なお話をいただけたことに感謝いたします。
次回は、大庄屋三木家の職務についてご紹介いただきます。
大庄屋の日々の姿をぜひお楽しみください。
<第2回 講座録>
日 時:平成22年7月3日(土) 13時30分~15時
演 題:「日本の七夕・播州の七夕」
講 師:尾崎織女氏(日本玩具博物館 学芸員)
7月3日、歴史民俗資料館にて、本年度第2回目の連続講座を開催しました。。
今回は「日本の七夕・播州の七夕」について、日本古来より伝わる七夕行事の歴史や
各地の行事紹介などを大変くわしく講演いただきました。
まず七夕の歴史については、文献史料に残された七夕行事の様子を1つ1つ紹介いただくことで、
時代の変遷が分かり、現代の七夕のルーツをたどることができました。
こうしたルーツを知ることで、播州の七夕飾りは江戸時代の七夕飾りの形態をよく残しており、
身近な行事の奥深い歴史の流れを学ぶことができました。
そして各地に伝わる七夕行事の紹介では、新聞等で馴染みのある地域の飾りや、
大変めずらしい七夕飾りを用いる地域など、様々な七夕行事を知ることができました。
このように、現在も地域に残る民俗行事の歴史を知り、より一層身近なものとして感じていただくことが
できたのではないかと実感します。
本日七夕を迎えるこの季節、このような素敵なお話をいただけたことを心よりお礼申し上げます。
次回は、福崎町の仏像についてご紹介いただきます。
仏像から見える地域の歴史をぜひお楽しみください。
<第1回 講座録>
日 時:平成22年5月22日(土) 13時30分~15時
演 題:「福崎でつながる地域の歴史~村史づくりの取り組みについて~」
講 師:松下正和氏(神戸大学大学院人文学研究科)
発 表:高橋部落史、板坂村史、田口村史、余田村史の取り組み紹介
5月22日、歴史民俗資料館にて、本年度第1回目の連続講座がはじまりました。
今年は、「地域の歴史文化遺産をつなげよう」をテーマに、地域の身近な文化財への
親しみを深めていこうと思います。
そこで、第1回目は町内の村史づくりについて皆さまから発表いただきました。
本講座では、地域の歴史資料と向き合い守り伝えていく経験をされてきた方々の様々な視点から
話を聞くことができました。
熱心に取り組まれるその力強い発表から、同じ地域に住む私たちはふるさとを思う心温かな気持ちや
励みを感じることができました。
そしてこうした地域歴史資料と向き合うことの大きな意義を知ることができたのではないでしょうか。
神戸大学からお越しいただいた松下先生からは、こうした発表から見えてくる村史づくりに
ついての要点や近隣の事例紹介をいただきました。
地域の歴史を「残そう」とする意識は、地域資源への再評価ともなるというお話や、
自治体史ではなく村史としてつくられた事例の発表を、この講座に参加いただいたみなさんと
共有することができた時間はとても大切なことだと教えていただきました。
本日はたくさんの方々の協力をいただき実現できたこと、心よりお礼申し上げます。
次回は、日本の七夕、そして播州の七夕についてご紹介いただきます。
7月、七夕を迎えるこの季節にぜひお楽しみください。
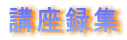
 平成21年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成21年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
 平成20年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成20年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
 平成19年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成19年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
 平成18年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成18年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
 平成17年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成17年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
 平成16年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成16年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
◆問合せ先◆
神崎郡歴史民俗資料館
℡:0790-22-5699
※お問合せ・お申込みは資料館まで。 |
|
 |
|
|
